
2025年2月25日、自由民主党・公明党・日本維新の会は2025年度予算案について三党合意をした。そこには、小学校の給食について2026年度より無償化するとの合意が書きこまれた。
▶ まずは小学校を念頭に、地方の実情等を踏まえ、令和8年度に実現する。
▶ その上で、中学校への拡大についても、できる限り速やかに実現する。
(「自由民主党、公明党、日本維新の会 合意」)
さらに、「Ⅳ 教育無償化に関する論点等」として、以下の記述がある。
2.いわゆる給食無償化については、地方自治体に対して、物価高騰対応重点支援地方創成臨時交付金を活用した対応を促すとともに、「学校給食法」との関係、児童生徒間の公平性、支援対象者の範囲の考え方、地産地消の推進を含む給食の質の向上、国と地方の関係、公立と私立の関係、現場レベルの負担といった論点について、十分な検討を行う。
(「自由民主党、公明党、日本維新の会 合意」)
最初の学校給食が始まってからおよそ150年、学校給食法が制定されてからおよそ70年の歴史において、特定の学校段階に限られるとしても、全国一律の無償が進められることは初めてである。大きな、大きな一歩であることは間違いない。しかし、この合意の実現によって、「隠れ教育費」研究室が全国オンライン署名において求めてきた「給食費無償」が達成されるといえるのか。残念ながら、それはいえない。
本当に子どもたちの〈食の権利〉保障を実現するものといえるのかは、合意の内容でも十分ではない上、今後の制度設計次第の部分もある。さらに言えば、合意の内容を見る限り、学校給食法の枠組みは改正することなく、政策予算による財政措置での対応となる可能性もある。その場合、2026年度予算以降でもこの方向性が継続するかは未知数である。
以上の認識を踏まえ、今後の展開において注視していくべき点について、確認していきたい。
〈合意の内容について〉
1.学校設置者の限定
合意の中では、「公立」などというように学校設置者の別を明記していない。上に示したように、公立と私立との関係は「論点」として挙げられており、今後に委ねられている。子どもの成長発達権が通う学校種によって差があるはずがない。公立・私立・国立、いずれの設置者であっても給食を提供している場合には無償の実現が果たされるべきである。
2.無償化の義務性
小学校については「地方の実情等を踏まえ」とある上、論点部分において、「地方自治体に対して、物価高騰対応重点支援地方創成臨時交付金を活用した対応を促す」とある。これは、これまで同交付金を活用して各自治体で給食費無償を進めてきた仕組みと同様ではないのではないかという危惧がある。つまり、国としては同交付金により小学校給食費の無償に向けた財源を用意しているけれども、それについて小学校給食費の無償に支出するかどうかは各自治体に委ねられるという危惧である。例えば地方の意思で無償化に参加するかしないかを選ぶことができるようなことが起こるのであれば、それは国として「小学校給食無償化」を実現したとは言えないのではないか。どのように「小学校給食無償化」に向けた縛りを各自治体にかけていくのか、きちんと見ていきたい。
3.中学校段階の保留
中学校について、「できる限り速やかに」ということで時限の設定がなされていない。これにより、中学校はいつまでたっても無償にならない、という状況はあってはならない。
〈制度設計について〉
A.給食の質保障の観点の欠如――「最低食単価(仮)」の設定
現状、給食費の金額は、物価や喫食数等の影響により地方により大きな差がある。国による負担額の設定においては、これらの差のある給食費(実績)の平均や最高額・最低額等を参照するのではなく、子どもたちの成長発達に必要な食材を十分に調達できる「最低食単価(仮)」を設定し、それが必ず担保される必要がある。それは、必要な額が最低限保障されなければ、栄養職員・栄養教諭が丹念に工夫を凝らしたとしても、学校給食栄養基準を満たすことは難しくなり、これまでよりも「給食の質が下がる」という残念なことが生じかねず、子どもたちの成長発達に影響が出るからである。そのため、その「最低食単価」は物価の変動を鑑みれば、最低でも1年に1回は見直される必要があり、また、地方における物価の格差を踏まえ、都道府県ごと、あるいは地域ごとにその食単価に差を設ける必要がある(その設計においては、地域別最低賃金が参考になるのではないだろうか)。
B.国の負担額を超える給食費の扱いは自治体負担に
自治体・学校によっては、国の負担額(「最低食単価(仮)」)を超えた金額を一食単価とし、ご当地メニューや地元食材を用いての給食など、工夫を凝らした献立を提供したいと考えることもあり得る。食育としての給食の意義を考えればこうした試み自体は歓迎されるだろうが、国の負担額を超える部分については設置者負担とし、保護者負担とすることは避けられなければいけない(これはアレルゲン除去食を喫食しており通常より割高となっている子の給食費も同様である)。家庭の経済力によって、食育が進められやすいところと進められにくいところが出てしまうからである。また、そうした工夫を凝らす場合も、成長期の子どもたちが喫食するにふさわしい、栄養基準を守った給食とすべきである。
C.完全給食が提供されていない子どもたちの〈食の権利〉保障
そもそも完全給食が提供されていない学校に通学している子どもたちには、現物支給としての給食は届かない。早々に学校給食法4条の給食提供について、設置者の努力義務から実施義務に改正するとともに、給食提供までの期間は給食費と同額を現金給付すべきである。選択制給食についても同様で、なるべく早くに全員制給食への移行を進めるべきだが、それまでは現金により同額を家庭に給付すべきだろう。
D.完全給食を喫食できていない子どもたちの〈食の権利〉保障
食物アレルギーのある子や不登校の子など、完全給食を喫食できていない子についての現金給付の仕組みも早急に構想される必要がある。最低限、喫食している子の給食費と同額の現金給付はあるべきだ。
E.教職員の給食費を給食指導の「経費」として見るべき
子どもたちの給食費徴収が行われない中で教職員についてのみ徴収を継続するのは、事務負担の視点からも不合理である。子どもたちの給食無償化が導入される際には、教職員の給食費についても給食指導・食育指導の「経費」として捉え学校設置者負担主義に基づき設置者負担とするか、受益者負担の論理を貫くのであれば、給食の時間は給食費を払っているすべての教職員が休憩時間(労働から解放されている時間)とすべきである。
(チーフアナリスト 福嶋 尚子)
▶ 該当記事
▶ 関連記事
▶ コラム著者
この記事が「参考になった!」と感じたら、周りの人に紹介したり、下記の「❤️(いいね!)」や「コメント」をしてもらえると嬉しいです♪






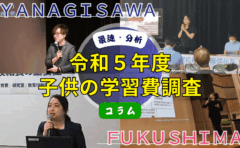
コメント